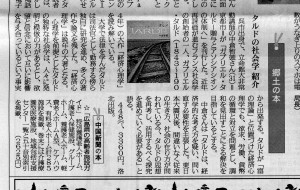〈1968年〉の神話化に抗して
―西川長夫『パリ五月革命 私論――転換点としての68年』を読む
2011年11月18日 16:30~19:30
立命館大学 末川記念会館 第2会議室
■企画趣旨:
「68年5月」(5月革命)から40年以上を経て刊行された西川長夫『パリ五月革命 私論』(2011年、平凡社)。本書は、1968年~1969年にかけて政府給費留学生としてパリに滞在した著者が、「私自身の目と身体と脳裏に刻まれた 68年革命の出来事」(本書p.10-11)を記した濃密なドキュメントである。このドキュメントは「同じ5月を生きた世代に、そしてその後に生を受けた 若い世代の人々に通じる普遍性をもちうること」(p.14)を期待して書かれている。つまり、現在における「革新的思想の再起動」(そで文)として世に送 り出されたのだ。
2000年代に入り大量に出版され続けている〈1968年〉論は、〈1968年〉の神話化、あるいは平板な歴史語りへと当時の出来事と経験を押し込めてい ないだろうか。たとえば、「あれは失敗だった」という今日の高みからの無惨な評価であり、「マイノリティとの関係性が欠落した運動だった」といった一面的 な評価が多いのではないだろうか。今必要なのは、〈1968年〉を大文字の歴史/出来事として考えるのではなく、〈1968年〉の多様な出来事・経験の複 層状況を明らかにすることだろう。また、〈1968年〉を思想・運動のピークとして特権化せずに、その前後の思想・運動との持続や転形のあり様を具体的に 検証することではないだろうか。つまり、〈1968年〉の神話化に抗する作業が求められている。
このような問題意識から、『パリ五月革命 私論』の合評会を開催したい。本合評会では、本書が描いた「パリ五月革命」の様々な出来事を批判的に読み解いて いきたい。具体的には、当時の大学制度への学生の異議申し立てと、そこから派生した多様な主体・思想・運動の形成と発展(ベトナム反戦運動、人種差別反対 運動、知識人論、文明批判、世界各地の運動との連帯を求める実践等)のあり様、「68年5月」を記述する著者の方法論、そして本書が今日の世界・日本の状 況に対して提起している課題などを、批判的に検討したい。合評者、そしてフロアの参加者が、それぞれの視点や研究・活動と『パリ五月革命 私論』との接点 や論点の広がりを提示・共有する場をつくりたいと思う。
▼日時: 2011年11月18日(金)16:30~19:30 (※終了後、懇親会を予定)
▼会場: 立命館大学 末川記念会館 第2会議室
http://www.ritsumei.jp/campusmap/map_kinugasa_j.html
▼内容:
・合評者による報告
箱田徹(立命館大学衣笠総合研究機構 ポストドクトラルフェロー)
http://www.arsvi.com/w/ht16.htm
橋口昌治(立命館大学衣笠総合研究機構 ポストドクトラルフェロー)
http://www.arsvi.com/w/hs01.htm
番匠健一(立命館大学先端総合学術研究科 院生)
http://www.arsvi.com/w/bk03.htm
・西川長夫氏からの応答
http://www.arsvi.com/w/nn03.htm
・フロア参加者を含むディスカッション
・司会・コーディネーター: 大野光明(立命館大学先端総合学術研究科 院生)
http://www.arsvi.com/w/om14.htm
▼主催: 立命館大学先端総合学術研究科 院生プロジェクト「植民地主義研究会」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/k/koubo2010-1.htm
(問い合わせ先: 大野 mitsuakick【あっと】hotmail.com)
▼参加費無料・事前申し込み不要