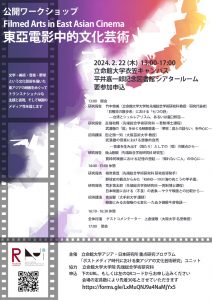立命館大学大学院先端総合学術研究科
『Core Ethics』Vol.20 2024年

◇目次 PDF<173KB>
◇奥付 PDF<64KB>
論文
ハンセン病療養所入所者が望む最期の場の選択
伊波 弘幸 p.1
PDF<431KB>
要約筆記事業と難聴者運動の歴史的検討
―パソコン要約筆記をめぐる意見の相違を手がかりとして―
押元 麻美 p.13
PDF<381KB>
台湾におけるパーソナル・アシスタンスの法制化プロセスにみる課題
高 雅郁 p.25
PDF<426KB>
「うんざりで不毛な仕事」が特別支援教育の実践にもたらす影響
―公立中学校教師へのインタビュー調査をもとに―
北見 由美 p.37
PDF<456KB>
専門化された世界への抵抗
―ミネラルコレクティングにおけるコレクターが持つ専門知を事例に―
孫 倩然 p.51
PDF<559KB>
将棋名人の地位の相対化
―終身制名人から実力制名人への移行に関する位置づけの変遷から―
松元 一織 p.63
PDF<456KB>
地元を離れて就労する
―暴力団離脱者の社会復帰を可能にする場をめぐって―
森 康博 p.75
PDF<462KB>
障害者に対する高等教育機関設置とその背景
―筑波技術短期大学設置を巡る経緯を通して―
山口 和紀 p.89
PDF<446KB>
「家庭保育が最善」であるとされるなか、保育所はどのような役割を付与されたのか
―1965 年版「保育所保育指針」制定過程の検討を通して―
山本 由紀子 p.103
PDF<409KB>
オンラインゲームにおける〈イレギュラープレイ〉
―中国における『Battlefield V』のプレイヤー行為の分析を通じて―
楊 思予 p.117
PDF<521KB>
理学療法士の国家資格化
―業務独占と開業権―
渡邊 宏樹 p.129
PDF<405KB>
批評
加藤旭人 著
『障害者と健常者の関係形成の社会学―障害をめぐる教育、福祉、地域社会の再編成と障害のポリティクス―』(花伝社2023 年)
大橋 一輝 p.141
PDF<191KB>
前之園和喜 著
『性暴力をめぐる語りは何をもたらすのか ―被害者非難と加害者の他者化―』勁草書房、2022 年、279 頁
加藤 このみ p.145
PDF<181KB>
川﨑寧生 著
『日本の「ゲームセンター」史 ―娯楽施設としての変遷と社会的位置づけ―』(福村出版、2022 年)
間宮 琴子 p.149
PDF<198KB>
大学院ウィーク企画
2023 年度 先端総合学術研究科大学院ウィーク 企画
『過去、未来、大学院の今を語る』 2023 年11 月10 日(金) 6 名の教員による座談会
出席者:美馬達哉、マーティン・ロート、小川さやか、後藤基行、竹中悠美、阿部朋恒 p.153
PDF<336KB>


.jpg)