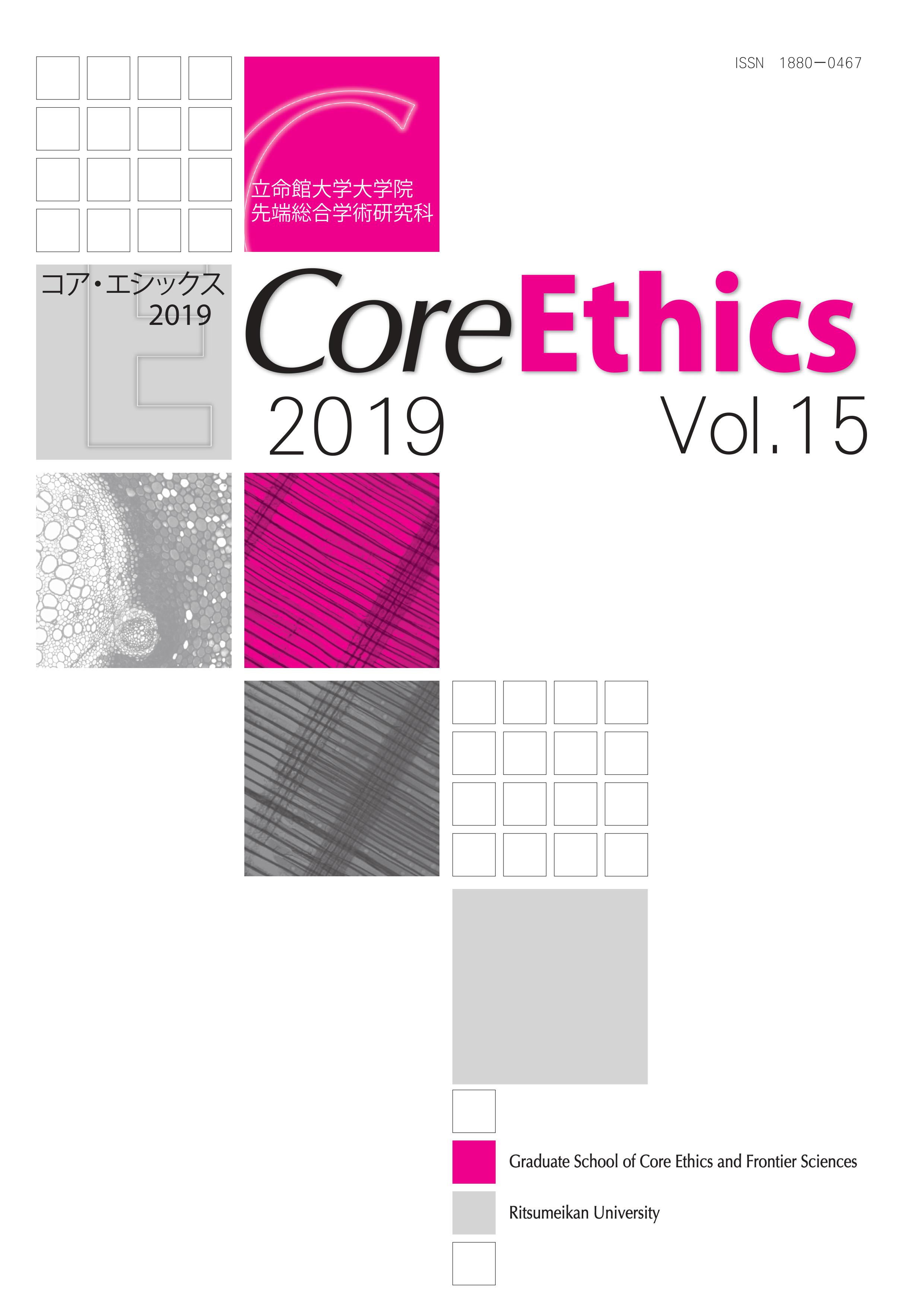院生代表者
- 張 憲
教員責任者
- 竹中 悠美
企画目的・実施計画
2018年度に引き続き、本プロジェクトの目的は日本、中国、台湾、韓国を中心とした東アジア地域における多様な美術、工芸、ファション、デザイン、サブカルチャーを各々メディアでありかつデザインとしての観点から学際的・包括的に研究することでる。
2019年度上半期においては、メンバーを集まり、東アジアにおけるメディアデザイン、特に今回の議題であるPost-Event Imagesについて、先行研究を背景に、メンバーそれぞれの研究領域から意見交換を行う。そして、下半期においては、台湾・台南美術館の学芸員Kuan, Hsiu-Hui(関秀恵)氏を招き、国際的オープンワークショップを行う予定であった。
活動内容
「実施計画」で述べたように、本年度のメインイベントとして、2020年3月4日(水)に講師としてKuan, Hsiu-Hui(関秀恵)氏を招聘し、「The Possibility of the Post-Event Images(事件/災難之後,影像如何可能?)オープンワークショップ」を開催する予定であったが、COVID-19の影響を受け、参加される方々の安全と健康を考慮した上、ワークショップを中止した。
成果及び今後の課題
ワークショップを中止せざるを得なかったが、本来の目的として、国際的ワークショップやフィールドワークの開催を通じ、台湾の映像研究についての情報を交換し、2018年度の欧米の先端メディアデザインと違った東アジアの視野を加え、より統合した理論を提示することができたであろう。そして、個人研究だけでなく、台南美術館などの研究施設間の交流を果たすことによって、各地域の研究連携を促進することも今後の課題として残されている。
構成メンバー
・張憲
・枝木妙子
・XU TING
・高見澤なごみ
・橋本真佐子
・李怡君
活動歴
2018年度の活動はコチラ


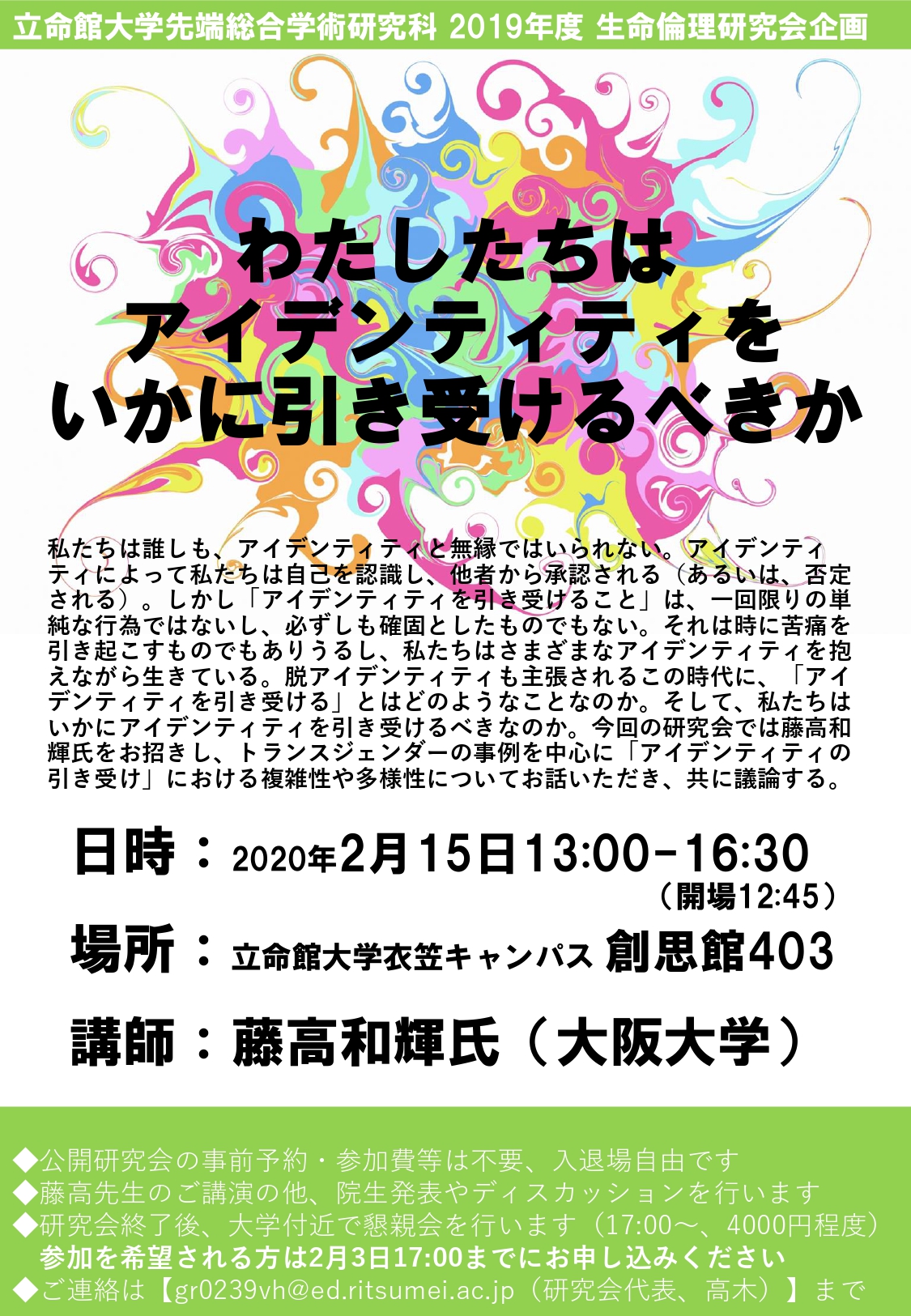
-1.jpg)