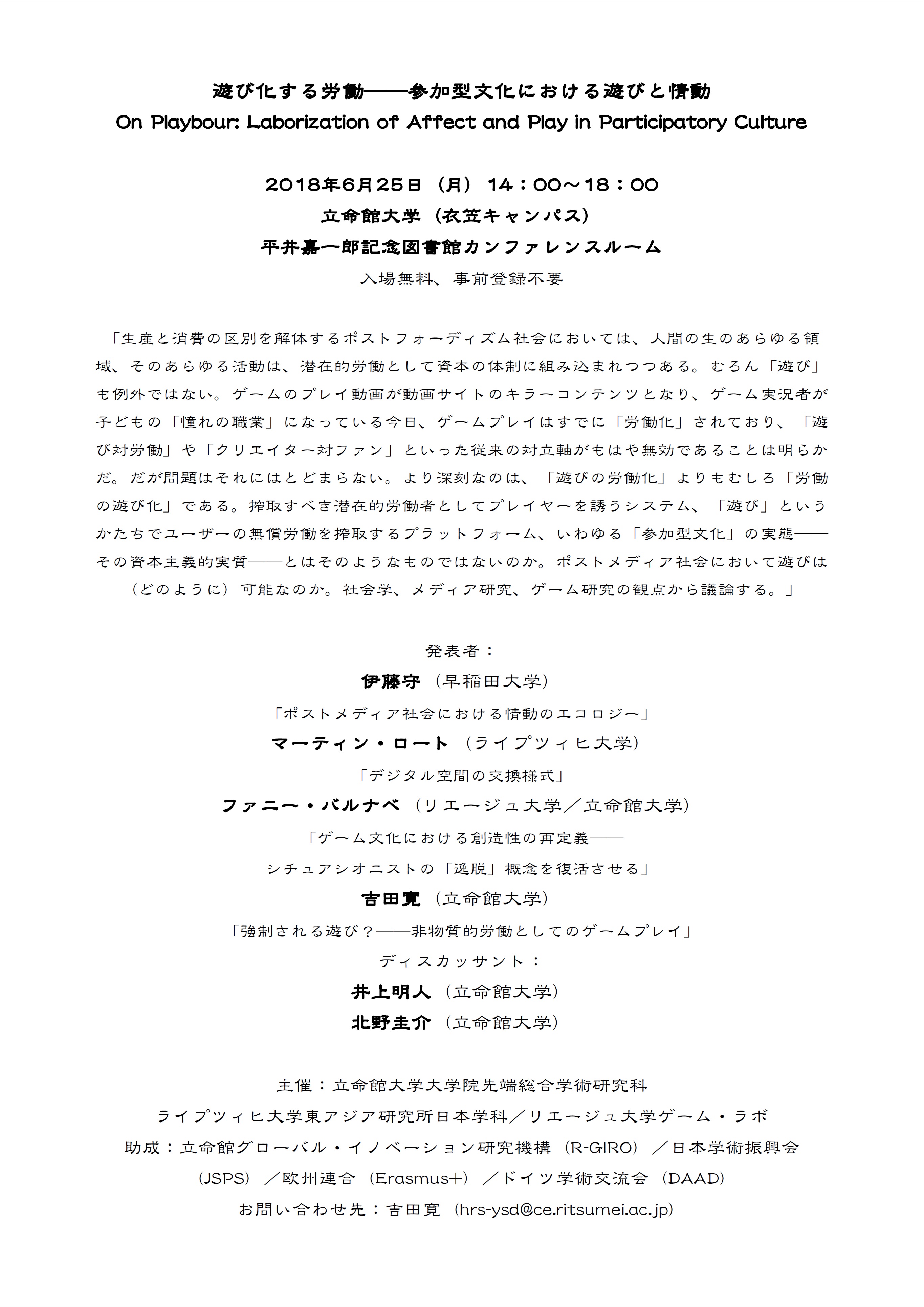- 映像編集ワークショップ開催
- 「音楽と社会」研究会 研究フォーラム
- 2018年度生命倫理研究会 公開研究会
- 安楽死のリアル 一つではない「良い死」」
- シンポジウム「都市と芸術のダイナミズム」
- Open Workshop Media Design in East Asia
東アジア・メディアデザイン研究会 公開ワークショップ - 2018年度 入試説明会日程
- 公開研究会「かわいいはベトナム!
──かわいいから探るベトナムのこれまでとこれから」 日時:2018年12月5日(水) 18:30開場 19:00開始
場所:MTRL京都(マテリアル京都)
◆入場無料・登録優先制(定員30名)◆
スピーカー:ジェニー・チャン・レ、トミザワ ユキ、西澤智子
主催:先端研院生プロジェクト「ディアスポラの文化経済活動実践としてのグローバルシネマ研究会」
*詳細はこちらをご参照ください。 - ベトナムフィルム上映会
日時:2018年12月4日(火) 15:00~17:30
場所:立命館大学衣笠キャンパス 充光館地階 JK001教室
◆参加無料・先着順(定員180名)・通訳あり◆
講師:ジェニー・チャン・レ Jenni Trang Le(映画プロデューサー)
コーディネーター:権藤千恵(先端研院生)
主催:立命館大学国際平和ミュージアム 平和教育研究センター
協力:先端研院生プロジェクト「ディアスポラの文化経済活動実践としてのグローバルシネマ研究会」
特別協力:ダン・ニャット・ミン(「サイゴンの少女ニュン」共同監督)
*詳細はこちらをご参照ください。 - ライスボールセミナー
- 立命館土曜講座〈特集 医療をめぐる法と倫理〉
- 公開シンポジウム
第1回 「マイノリティ・アーカイブズの構築・研究・発信」 - 立命館大学大学院先端総合学術研究科紹介の集い in 京都
鼎談 岸政彦×小川さやか×松尾匡
「楽しい反緊縮──借金返さナイト」 - 立命館大学大学院先端総合学術研究科紹介の集い in 東京
「勉強する、研究する
―立岩真也と千葉雅也における「読み書きそろばん」―」 - 2018年度大学院ウィーク 終了しました
- 「トランスメディアル・アジア──第4回・ライプツィヒ大学・立命館大学共同企画ワークショップ『ローカルとグローバルの中の日本のビデオゲーム』」を開催します終了しました
- 講演会「イタリア・ボローニャでの精神障がいと地域との共生の歩み──よりあたりまえな地域社会の実現に向けて」終了しました
- 講演会「この国に生まれたる不幸を重ねないために──座敷牢から地域での暮らしへ」 終了しました
- 公開シンポジウム「スラムツーリズムの展開――その多様性と創造性」を開催します 終了しました
- 院生プロジェクト・「ビデオエスノグラフィー・会話分析研究会」第1回研究会を開催します 終了しました
- 遊び化する労働──参加型文化における遊びと情動
On Playbour: Laborization of Affect and Play in Participatory Culture 終了しました - 2018年度 入試説明会日程
立命館大学の映像人類学院生プロジェクトでは3/18,19の2日間にかけて小田昌教/イルコモンズ先生を講師に迎えて映像編集のワークショップをします。初日はレクチャー、2日目が実習となり、映像のリテラシーを知識として身につけるとともに、実習を通じて身体的な理解を促す、21世紀の知の基礎講座になります。
【タイトル】立命館映像編集ワークショップ
【講師】小田昌教/イルコモンズ
【日時】3/18(月) 14:00-17:00頃 レクチャー
3/19(火) 14:00-17:00頃 実習
【場所】立命館大学 衣笠キャンパス 有心館YS201
【参加人数】10名程度
内容や申し込み方法等詳細についてはこちらをご覧ください。
日時 2019年2月17日(日)12:00~17:45
場所:立命館大学衣笠キャンパス学而館312教室
主催:院生プロジェクト「音楽と社会」研究会
日時 2019年2月9日(土)開場13:00、13:30~16:50
場所:キャンパスプラザ京都 第一演習室(5階)
講師:佐々木拓先生(金沢大学)
主催:院生プロジェクト 生命倫理研究会
日時 2019年2月2日(土)午後2時30分〜
場所:立命館大学朱雀キャンパス多目的室(予定)
主催:立命館大学 生存学研究センター
後援:立命館大学先端総合学術研究科
日時 2019年1月19日(土)13時〜17時
場所:立命館大学衣笠キャンパス 立命館大学衣笠キャンパス 学而館301号室
主催:先端研院生プロジェクト「「音楽と社会」研究会」
日時 2018年12月14日(金)13時〜18時
場所:立命館大学衣笠キャンパス 究論館カンファレンスルームB・C
主催:先端研院生プロジェクト「東アジア・メディアデザイン研究会」
+アジア日本研究推進プログラム「『アジア芸術学』の創成」
言語:英語
日時:2018年11月18日(日)12:00~12:40(全体説明会)、12:50~13:50(研究科別相談会)
場所:立命館大学衣笠キャンパス 敬学館
参加教員:小泉義之、岸政彦、小川さやか、千葉雅也
参加院生:公共領域・平安名
日時:2018年11月23日(金・祝)17:20~18:00(全体説明会)、18:10~19:10(研究科別相談会①)、19:20~20:20
(研究科別相談会②)
場所:大阪いばらきキャンパス(OIC) A棟
参加教員:岸政彦、竹中悠美
日時:2018年12月12日(水)16:20~17:00(全体説明会)、17:10~18:10(研究科別相談会①)、18:20~19:20
(研究科別相談会②)
場所:立命館大学衣笠キャンパス 敬学館
参加教員:小泉義之、美馬達哉、西成彦
参加スタッフ:表象領域・田邉
日時:2018年11月20日(火)12:20~12:50
場所:立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム
発表者:枝木妙子(先端研院生)
テーマ:戦中期の新聞・婦人雑誌におけるファッションとしてのモンペ
当日の様子はこちら→ 開催報告(ライスボールセミナー 公式facebook)
日時:2018年12月4日(火)12:20~12:50
場所:立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム
発表者:野島晃子(先端研院生)
テーマ:“コミュニケーション能力”に翻弄されるわたしたち
当日の様子はこちら→ 開催報告(ライスボールセミナー 公式facebook)
講座テーマ:優生保護法問題からみる医療の倫理(第3260回)
日時:2018年12月1日(土)14:00-16:00
場所:立命館大学 末川記念会館SK101(講義室)
講師:松原洋子(先端研教員)
◆聴講無料・事前申込不要◆
企画:立命館大学人文科学研究所
主催:立命館大学衣笠総合研究機構
日時:2018年12月1日(土)10:30–18:45
場所:立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム
◆参加費無料、当日参加可能◆
主催:立命館大学生存学研究センター
*詳細はこちらをご参照ください
日時:2018年11月30日(金)19:00-21:00
場所:マテリアル京都
◆予約制(50名)・入場無料◆ *ビールorドリンク有(別途料金)
日時:2018年11月11日(日)14:00-17:00
場所:ステーションコンファレンス東京4F
◆要事前申込・参加費無料◆
日時:2018年9月24日(月・祝)13:00-16:30、25日(火)13:00-18:00
場所:立命館大学衣笠キャンパス 平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルーム
*詳細はこちらをご参照ください
日時:2018年9月29日(土) 14:10~15:10
場所:福井メトロ劇場
講師:イヴォンヌ・ドネガーニ(ボローニャ精神保健局元局長)
指定質問:三浦藍(人間環境大学)、伊東香純(立命館大学 先端総合学術研究科)
司会:幸信歩(福井医療大学)
主催:院生プロジェクト「精神医療史・医学史研究会」、「呉映画を通して精神障がい者が地域で生きるを問い直す」実行委員会、福祉医療大学
協力:きょうされん福井支部、NPO法人東京ソテリア
*詳細はこちらをご参照ください
日時:2018年9月30日(日) 10:00~11:45
場所:福井市地域交流プラザ・アオッサ6階 601会議室
講師:イヴォンヌ・ドネガーニ(ボローニャ精神保健局元局長)
指定質問:桐原尚之(全国「精神病」者集団・運営委員)
司会:幸信歩(福井医療大学)
主催:院生プロジェクト「精神医療史・医学史研究会」、「呉映画を通して精神障がい者が地域で生きるを問い直す」実行委員会、福祉医療大学
協力:きょうされん福井支部、NPO法人東京ソテリア
*詳細はこちらをご参照ください
日時:2018年8月3日(金)10:00~14:50
場所:立命館大学 衣笠キャンパス 創思館303・304
*詳細はこちらをご参照ください
日時:2018年7月29日(日曜日)9:00~12:00
場所:キャンパスプラザ京都 第2会議室
*詳細はこちらをご参照ください
日時:2018年6月25日(月)14:00~18:00
場所:立命館大学(衣笠キャンパス)
平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルーム
◆入場無料、事前登録不要◆
発表者:
伊藤守(早稲田大学)
マーティン・ロート(ライプツィヒ大学)
ファニー・バルナベ(リエージュ大学/立命館大学)
吉田寛(立命館大学)
ディスカッサント:
井上明人(立命館大学)
北野圭介(立命館大学)
日時:2018年5月25日(金)16:20~19:50 終了しました
場所:立命館大学衣笠キャンパス 敬学館
参加教員:岸政彦、小泉義之、千葉雅也、P・デュムシェル
参加院生:表象領域院生
日時:2018年6月10日(日)12:00~15:00 終了しました
場所:大阪いばらきキャンパス(OIC) A棟
参加教員:岸政彦、松原洋子
日時:2018年6月17日(日)12:00~15:00 終了しました
場所:立命館大学衣笠キャンパス 敬学館
参加教員:小川さやか、小泉義之、立岩真也、吉田寛
参加院生:公共領域院生