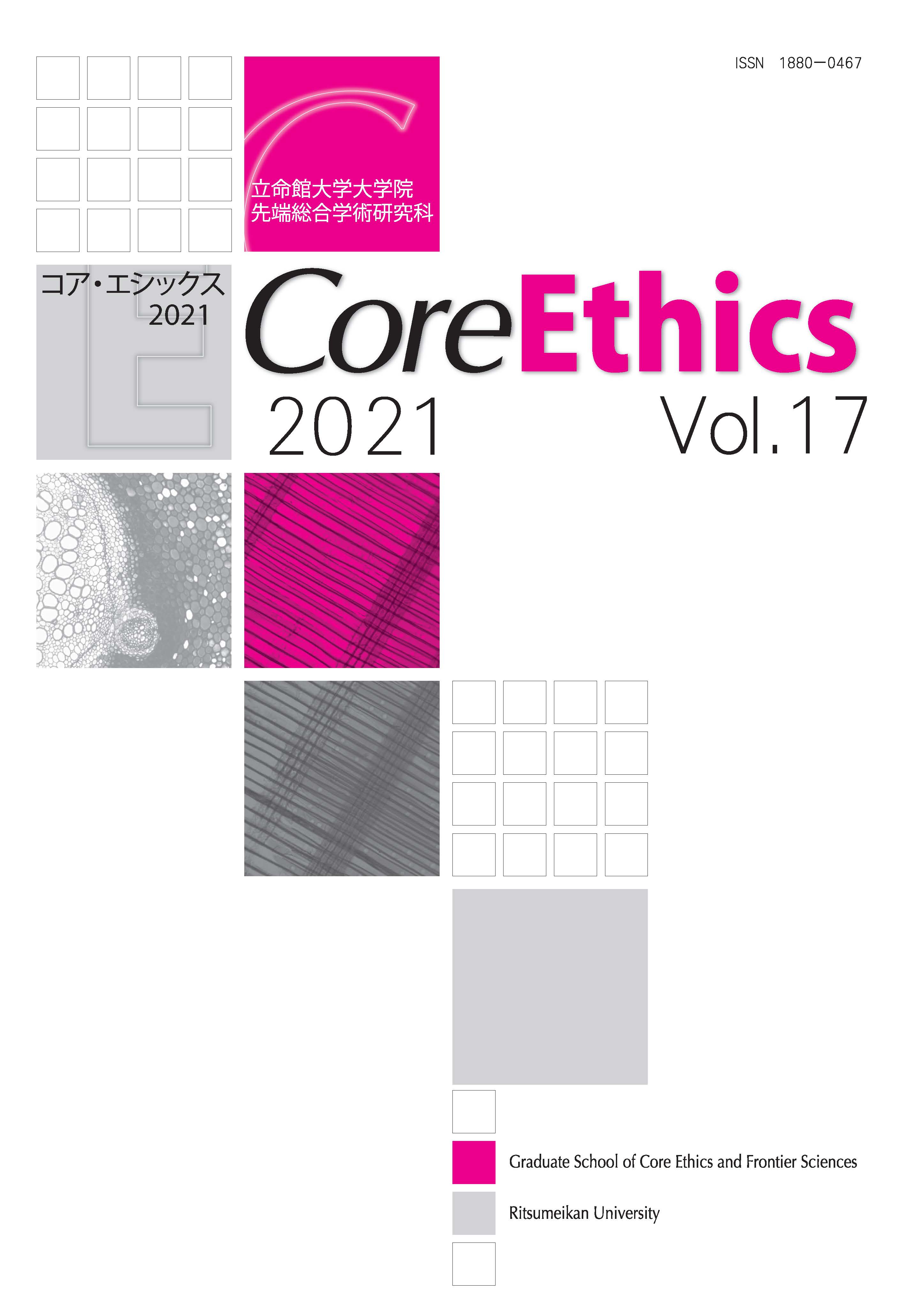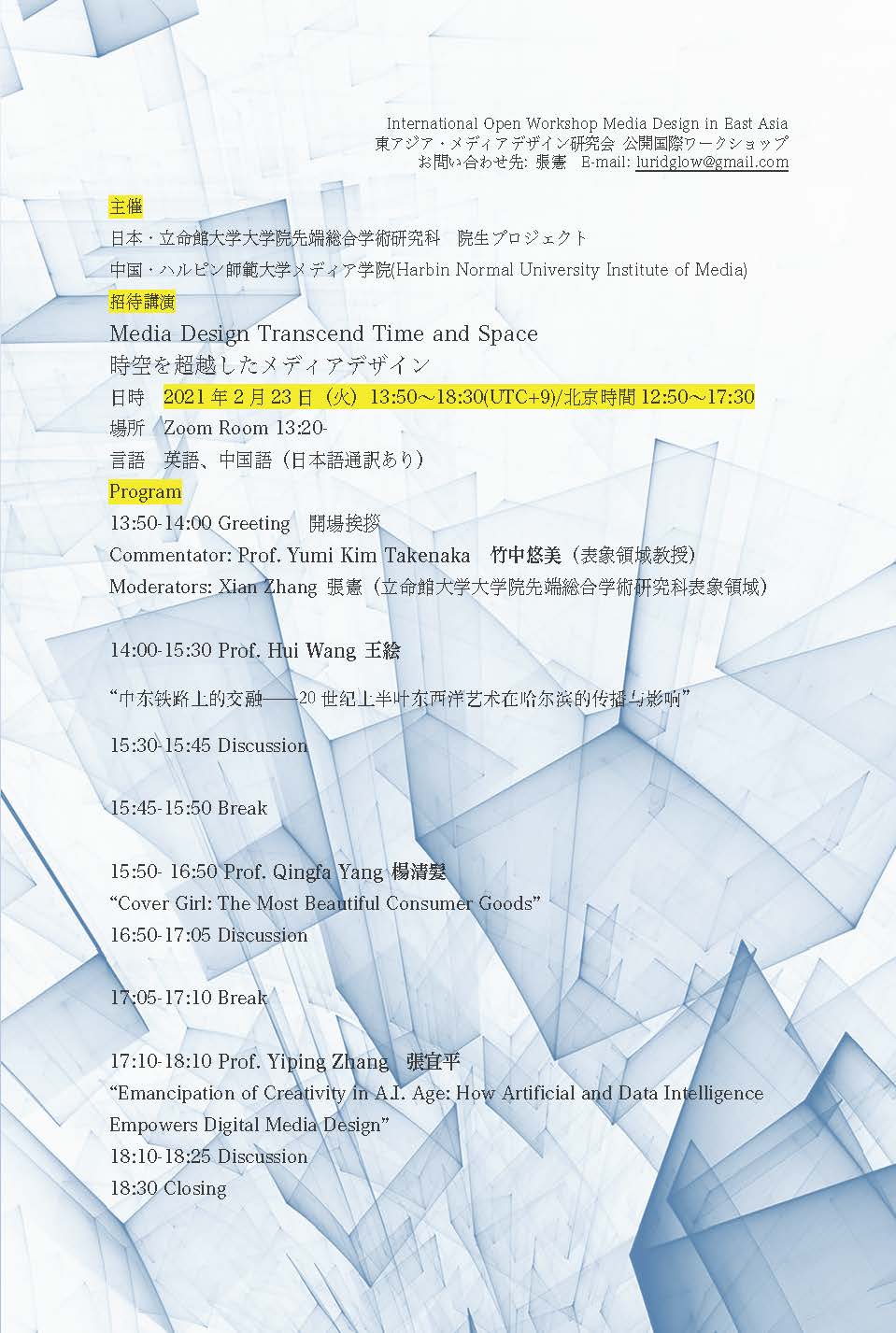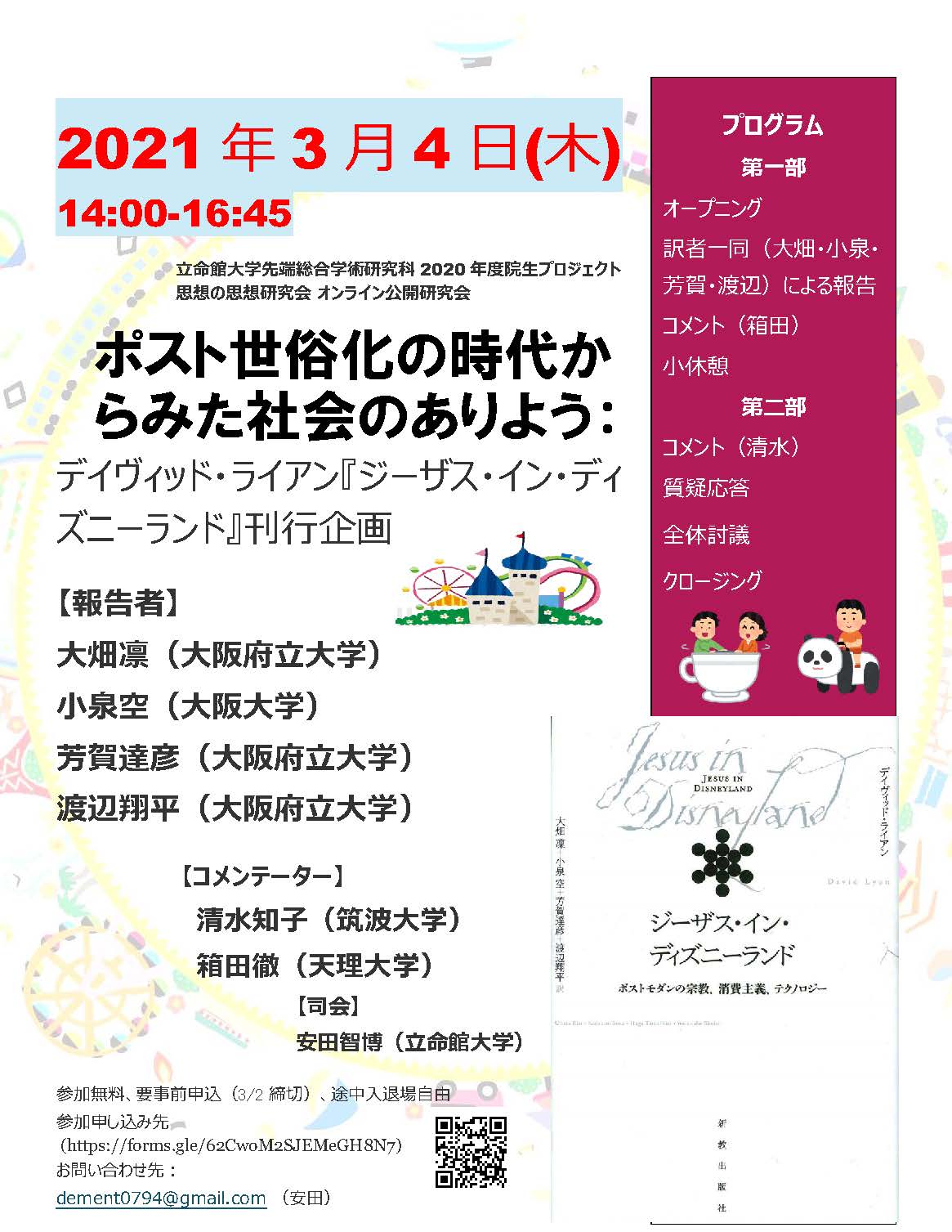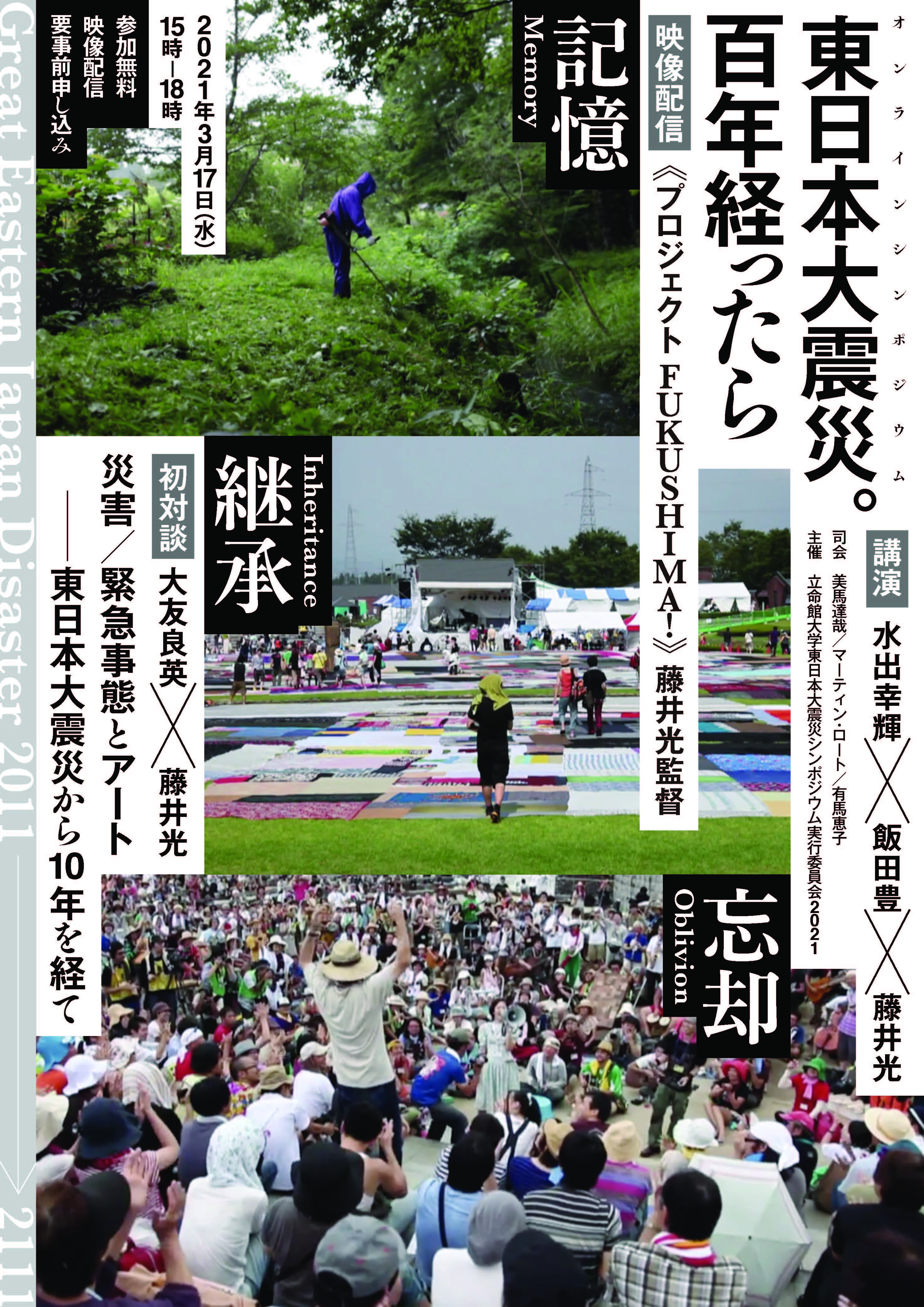院生代表者
- OUYANG Shanshan
教員責任者
- 立岩 真也
概要
【目的】
SOGI(Sexual Orientation and Gender Identity)とは、性的指向とジェンダー・アイデンティティのことを意味する。本研究会はSOGIの視点で幅広い課題を検討することを目指している。2021年度研究会の目的は、クィア理論、フェミニズムにとって重要な文献であるGender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Butler, 1990)を精読した上で、ディサビリティ・スタディーズと交差する検討を行う。また、社会問題を着目し、これからの研究課題を検討することである。
【内容と方法】
本研究会の内容および方法は3つの活動で構成される。
①読書会を開催し、『ジェンダー・トラブル』を精読し、関連文献・論文の輪読を行うことを活動の基本とする。その場、担当メンバーがレジュメを作って発表する。
②外部講演会や外部の研究会に参加し、その場で得た知識と自分なりの感想などを研究会で検討する。
③読書会で検討したテキストの著者を招きして公開研究会を行う。
【意義】
本プロジェクトは、多様な専門領域とSOGIの接点を探ることによって、クィア理論、ディサビリティ・スタディーズに関心を持つメンバーは各自の研究を進捗させると考える。
活動内容
1)文献の講読
今年度は8回分けて、Butler, Judith, 1990, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge. (=竹村和子訳, 1999,『ジェンダー・トラブル――フェミニズムとアイデンティティの攪乱』青土社). を講読し、議論を行った。
日時: 2021年4月25日、5月30日、6月27日、8月1日、9月4日、10月17日、11月21日、2022年1月16日
場所: Zoom(オンライン)
2)公開研究会の開催
①2022年2月13日に、「バトラーの議論を引き受けて」と題して、公開研究会を開催した。これまでのバトラーの議論を参照しつつ、バトラーの理論を踏まえたフェミニスト現象学や文学分析との結びつけに焦点を当てて議論をした。講演は羽生有希氏「フェミニスト現象学の継承としての『ジェンダー・トラブル』」である。院生発表は、メンバーである森祐香里「〈肉体〉を思考する場としての文学 ―第二次世界大戦直後日本における肉体文学研究から」であり、その後、参加者を含めた総合討論を行った。
文献閲読:
羽生有希,2019,「来たりし、来たるべきフェミニスト哲学――フェミニスト現象学とジェンダー・パフォーマティヴィティ」『現代思想総特集 ジュディス・バトラー』47(3):130-144.
- 公開研究会「バトラーの議論を引き受けて」
日時:2022年2月13日(日) 13:00~16:00
場所:Zoom
②2022年2月25日に、「バトラー・政治・身体」と題して、公開研究会を開催した。ジュディス・バトラーの『ジェンダー・トラブル』は1990年に出版されたが、今もなお、議論を巻き起こし、クィア理論に限らずさまざまな分野に影響を及ぼし続けている。講演の五十嵐舞氏は、911以降のアメリカ社会問題をバトラーの議論に結びつけ検討し、そして日本の性差別とジェンダー問題を提示した。その後、参加者を含めた総合討論を行った。
文献閲読:
五十嵐舞,2019,「複数の『わたし』による連帯――ジュディス・バトラーの集合の政治と差異」『現代思想総特集 ジュディス・バトラー』47(3): 225-234.
――――,2021,「ままならない身体、ままならない情動――ジュディス・バトラーの『パフォーマンスティヴィティ』と『プレカリティ』」『帝国のヴェール――人種・ジェンダー・ポストコロニアリズムから解く世界』164-170.
- 公開研究会「バトラー・政治・身体」
日時:2022年2月25日(金) 14:00~16:00
場所:Zoom
構成メンバー
OUYANG Shanshan
SHEN CHIN
長島 史織
QU Honglin
宮内 沙也佳
勝又 栄政
森祐 香里