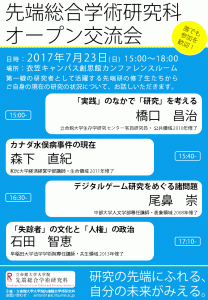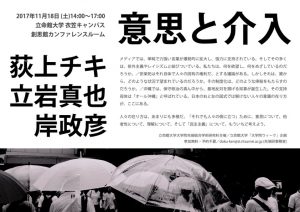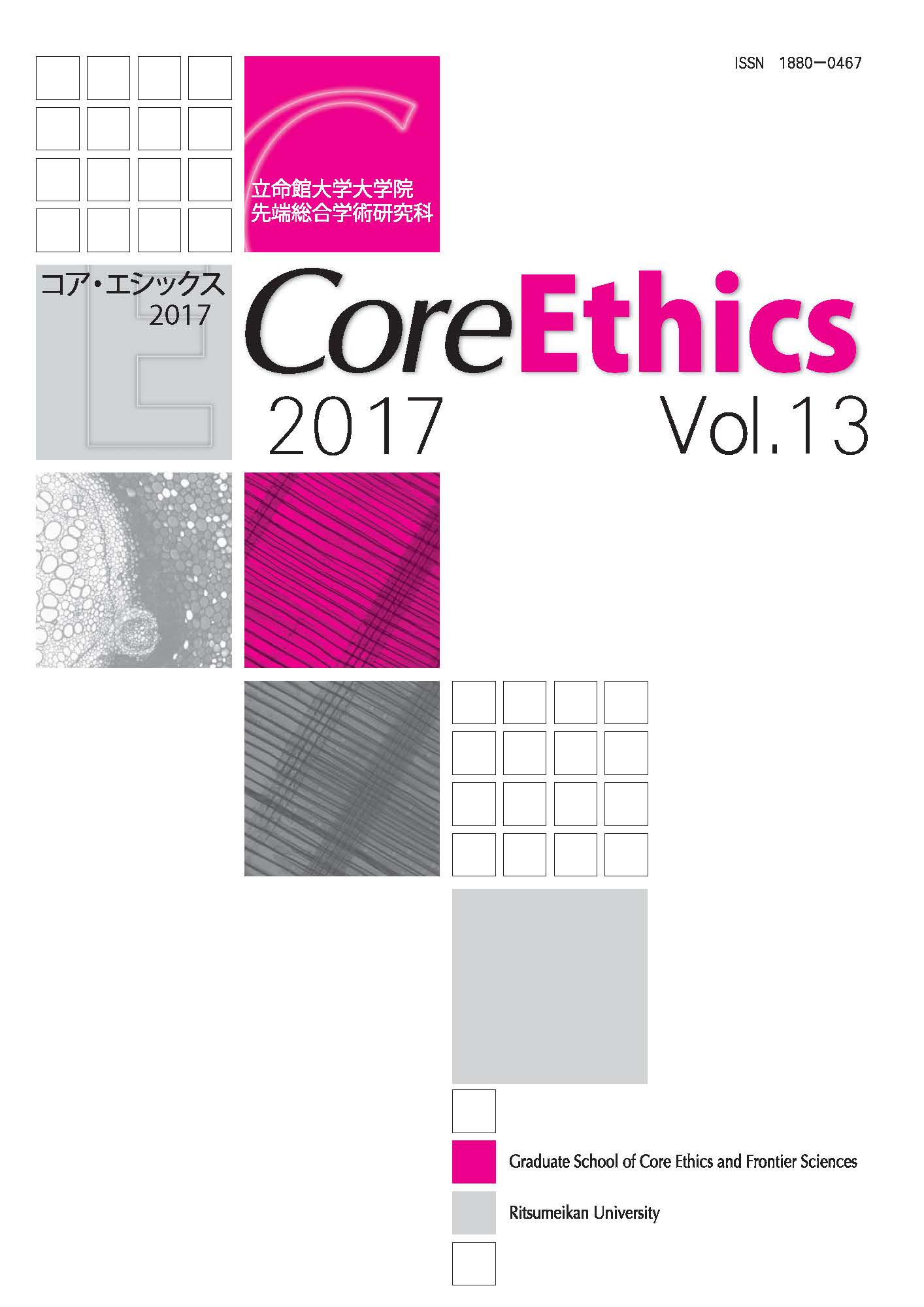立命館大学大学院先端総合学術研究科
『Core Ethics』Vol.13 2017年
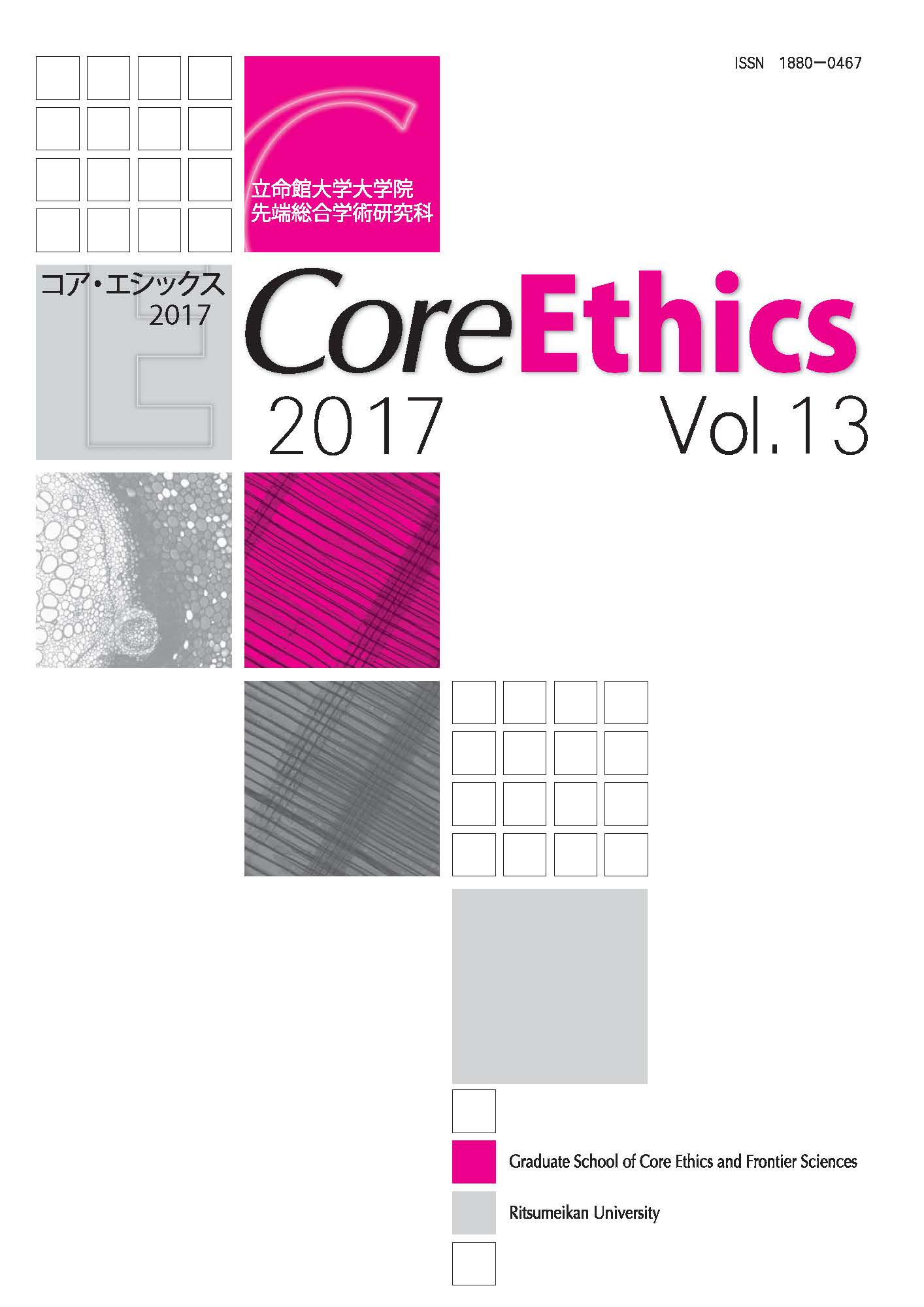
◇目次 PDF<212KB>
◇奥付 PDF<55KB>
◇正誤表 PDF<162KB>
論文
支援された意思決定と代理意思決定の違い
――国連障害者権利条約採択までの過程から――
伊東 香純 p.1
PDF<301KB>
生態学的な情報の再考
――ヴァーチャル空間に対するアフォーダンスの適用に向けて――
伊藤 京平 p.13
PDF<343KB>
ニューカマーの日韓ダブルの「祖国留学」から見るエスニックアイデンティティの考察
――オールドカマーとの比較から――
今里 基 p.25
PDF<441KB>
関西における障害者解放運動をけん引したある盲人の青年期
――楠敏雄を運動へ導いた盲学校の経験――
岸田 典子 p.37
PDF<442KB>
医療的ケア児に対するレスパイトを目的とした訪問看護の検討
金野 大 p.49
PDF<409KB>
脊髄損傷者の理学療法における起立・歩行訓練
――1960 年代~1980 年代の「歩行」言説分析から――
坂井 めぐみ p.61
PDF<445KB>
公共の場の語りによる精神障害当事者のエンパワメントの獲得過程とその特徴
――語り部グループ「ぴあの」の語りの実践から――
栄 セツコ p.73
PDF<456KB>
コールバーグの道徳性発達理論と法的発達
――第5 段階と刑事司法の特質との関係から――
佐藤 伸彦 p.87
PDF<364KB>
恵那地方の「「障害者」地域生活運動」
――廃品回収による社会的ネットワーク――
篠原 眞紀子 p.99
PDF<600KB>
米軍統治下の沖縄離島集落におけるハンセン病をめぐる状況
――離島に駐在する公衆衛生看護婦の役割を中心に――
鈴木 陽子 p.113
PDF<402KB>
非配偶者間生殖補助医療におけるカウンセリングの位置づけ
――厚生科学審議会生殖補助医療部会議事録から分析する――
瀧川 由美子 p.125
PDF<377KB>
オプション価格決定理論における時間概念
椿井 真也 137
PDF<604KB>
大阪の過労死運動と大阪過労死を考える家族の会結成の経緯
――過労死運動の展開における過労死家族という当事者の出現――
中嶌 清美 p.149
PDF<386KB>
京都市における生活保護「適正化」政策
――「暴力団員等」対策事業の展開――
中村 亮太 p.161
PDF<392KB>
メディアスポーツ「野球」におけるカメラアングルの変遷
根岸 貴哉 p.173
PDF<334KB>
『月映』の同人活動
――北原白秋への献本を通じて――
橋本 真佐子 p.185
PDF<628KB>
日本認知症ケア学会抄録集の分析からみた認知症ケアにおける非薬物療法の動向
畑野 相子 p.199
PDF<447KB>
「文化主体性論」の再考
――ケニア・ナイロビ市におけるスラムツーリズムの展開を事例に――
八木 達祐 p.211
PDF<430KB>
『non-no』と『MEN’S NON-NO』から見た若者向け雑誌における言語表現
劉 雨瞳 p.223
PDF<435KB>
研究ノート
いかに在宅看取りが選ばれるのか
――親の病院死と在宅死を経験した女性の語りから――
桶河 華代 p.235
PDF<465KB>
批評
谷崎の見た着物と女
枝木 妙子 p.247
PDF<301KB>