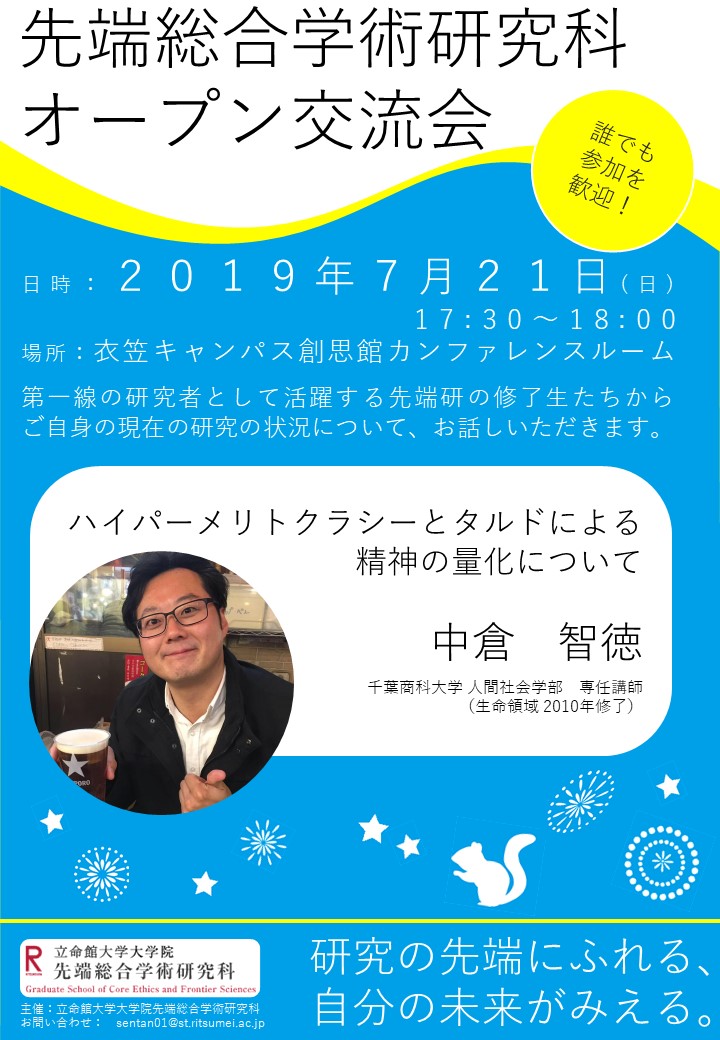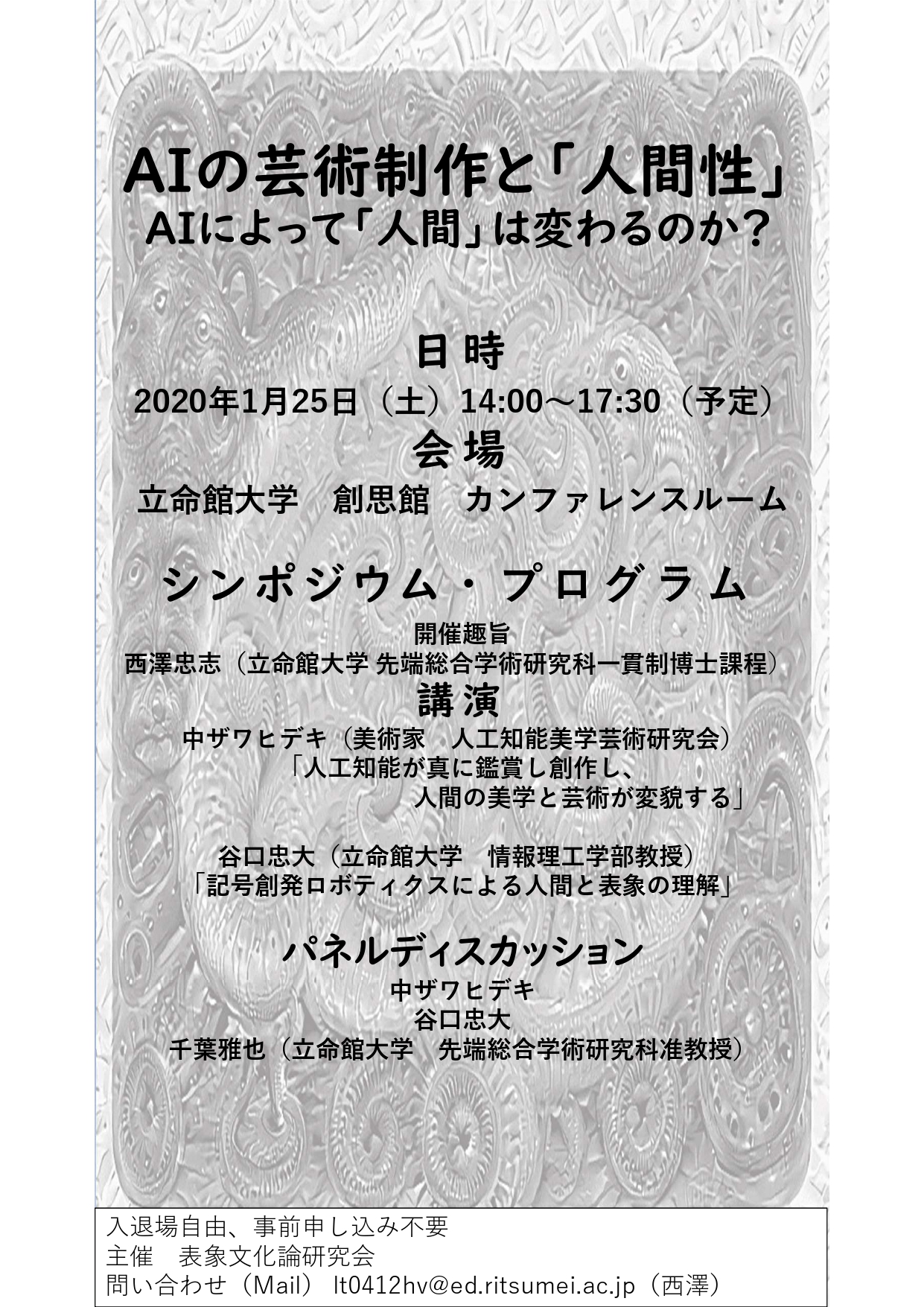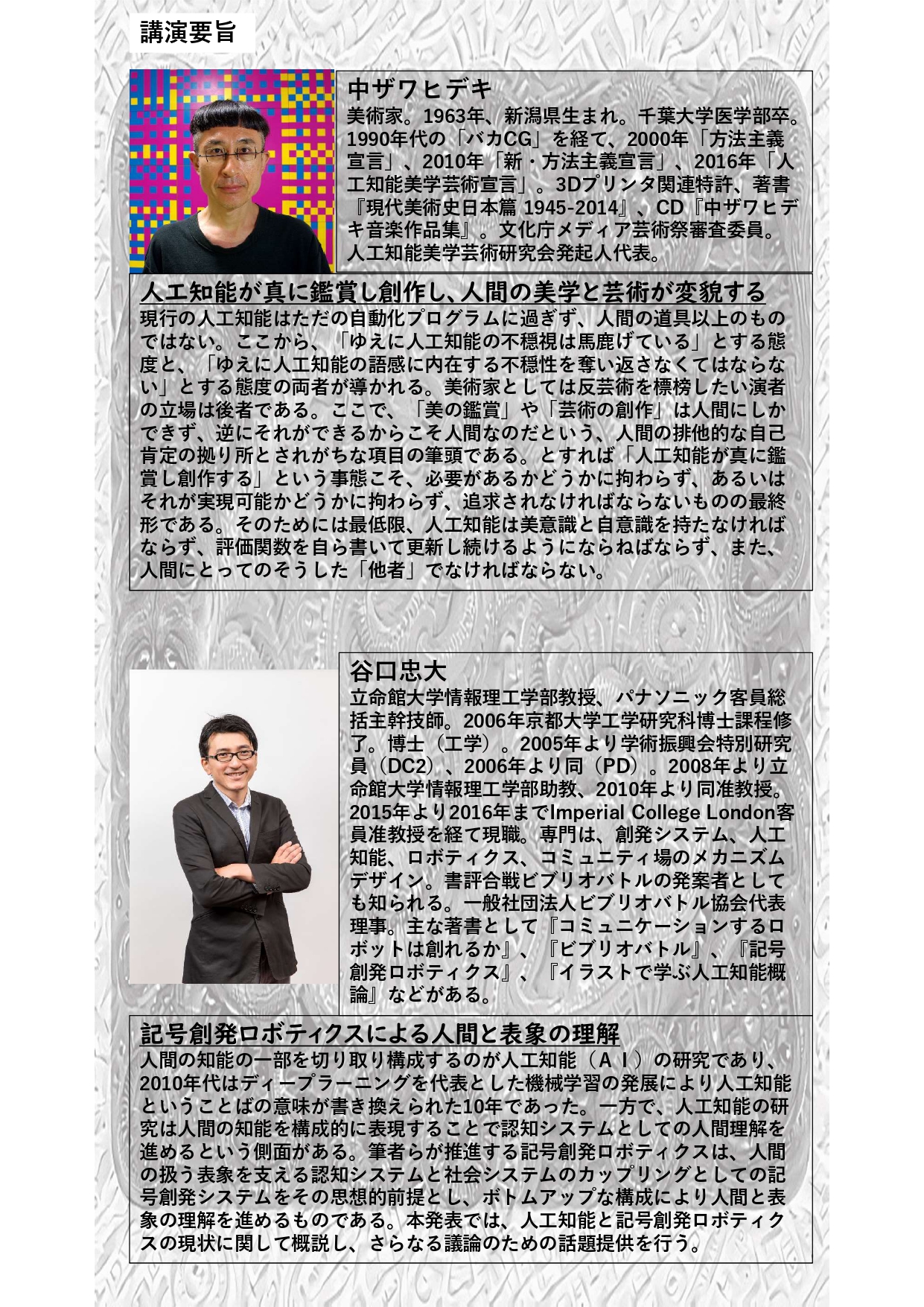院生代表者
教員責任者
企画目的・実施計画
テーマ:精神障害者に対する恣意的拘禁の例を中心にした政府と同作業部会、NGOの効果的な連携
講 師:Seong-Phil Hong(国連人権理事会恣意的拘禁作業部会前座長)
日 時:2019年6月2日(火) 10時30分 ~ 12時30分
場 所:参議院議員会館地下1階・B109会議室
活動内容
国連人権理事会恣意的拘禁作業部会、特別手続及び個人通報、訪問(Official country visit)の事例、能力開発(Capacity building)と技術的援助(Technical assistants)の事例、国連自由を剥奪された人の法廷における救済と手続きの権利についての基本原則とガイドライン(United Nations Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of Their Liberty to Bring Proceedings Before a Court)の分析、日本の精神医療に対して恣意的拘禁を判断した勧告二例の分析に関する講演をおこなった。
参加人数:56人
成果及び今後の課題
国連人権理事会恣意的拘禁作業部会は、次のような経緯で設立された特別な機能をもつ部会である。
旧人権委員会(仮名53か国)は、1985年以降、恣意的拘禁の拡がりに取り組んでいる。同委員会は1990年、差別防止・少数者保護小委員会に対し、この問題に関する詳細な調査を行い、そうした慣習を縮小させるための提言を同委員会に提出するよう要請した。
また、1988年12月に国連総会が「あらゆる形態の抑留または拘禁の下にあるすべての者の保護のための諸原則」を採択した際、自由を剥奪されたすべての人が享受すべき保障に関し、懸念が表明された。
1991年には旧人権委員会が決議1991/42で、恣意的拘禁作業部会を立ち上げた。
2006年に国連総会が2006年4月3日の決議60/251で人権理事会を設置し、その後、同理事会が2006年11月13日の決定1/102で、旧人権委員会のすべてのマンデートを引き受ける旨を決定した。
2016年9月30日、人権理事会の決議で33/30で恣意的拘禁作業部会のマンデートは3年間延長された。
恣意的拘禁作業部会は、通常3回(4月、8月、11月)会議を開催する。各会議では25から40の意見が採択され、必要に応じて一般意見、国別報告、年次報告が採択される。
WGADは、特別手続き、救済機関および準司法機関としてそのマンデートを履行する目的でその性質と機能の確立を図る一方で、事実を調査する任務を果たし、個人の被害者に救済を与え、拘禁関連の国際規範に基づく諸判例の蓄積に努めている。
そのマンデートは、次の通り詳細に示すことができる。
(a)恣意的、または関係国際基準に矛盾する自由剥奪の事例を調査すること。
(b)各国政府や政府間組織、非政府組織からの情報を求め、受領し、関係する個人、その家族や代理人から情報を受理すること。
(c)恣意的拘禁が疑われる事例に関して知らされた情報に関し、当該事例を明確化し関係政府に知らせる緊急要請や連絡を関係政府に送付することで行為すること。
(d)各国で広がりを見せる恣意的自由剥奪の状況や、恣意的自由剥奪事例の背後にある理由について理解を深めるため、政府の招聘に基づき現地で任務を実施すること。
(e)加盟国が恣意的自由剥奪を予防し、そうした習慣から保護するのを支援し、将来の事例に関する検討を促進することを目的として、一般的な性質の問題に関する一般意見を形成すること。
(f)その活動、調査結果、結論および提言を示した年次報告を人権理事会に提出すること。
さらに、人権理事会は、同作業部会がそのマンデートを履行するにあたり、次の事項を行うよう奨励する。
(a)作業部会に提出された事例に懸念を示すあらゆる関係者と、特に適切な検討が行われるべき情報を提供する加盟国と、協力・対話を行いながら取り組むこと。
(b)人権理事会の他のメカニズム、他の国連所轄機関および条約機関と協調して取り組み、その協調においては、国連人権高等弁務官事務所の役割を念頭に置くこと、また、特に作業部会が受領する連絡の取り扱いや現地での林務に関し、これらのメカニズムとの重複を避けるために必要なすべての措置を講じること。
(c)裁量権、客観性および独立性を持って作業を行うこと。
意見
WGADは、自由剥奪が恣意的か否か判断するための基準を採択した(改訂ファクトシート第26号参照)。WGADは、個人からの申立ての検討について明確に定めたマンデートを持つ唯一の非条約メカニズムである。WGADの行為は、被害者が各地の救済手段をすべて行使したか否か、対象となっている加盟国が特定の条約の当事国であるか否かにかかわらず、世界各地の個人の請願権に基づくものである。
同作業部会は、恣意的拘禁の疑われる事例に関し、個人または非政府組織から寄せられた通報で提示される情報や、各国政府、政府間組織からの情報に基づき行為する。
連絡は関係政府に送付され、申立てに関するコメントおよび意見を事実および適用法の観点、また命じられた調査の進捗状況および結果の観点から、60日以内に作業部会に伝達する機会が与えられる。
政府から作業部会に送付された回答は、最終のコメントまたは意見用として情報源に送付される。この対立構造のため、WGADには準司法メカニズムの地位が認められる。
意見―類型
WGADは通例、次の5つの法的類型を参照しなければならない。
(a)人が刑の終了後も、または恩赦法が適用されるにもかかわらず、拘禁され続ける場合のように、自由剥奪を正当化する法的根拠を引合いに出すことが明らかに不可能である場合(第1類型)
(b)自由剥奪が、世界人権宣言の第7条、第13条から第14条および第18条から第21条、加盟国当事者に関しては、市民的および政治的権利に関する国際規約の第12条、第18条から第19条、第21条から第22条および第25条から第27条で保証された権利または自由の行使に起因する場合(第2類型)
(c)世界人権宣言および関係加盟国が承諾した関連国際文書に規定された公正な裁判を受ける権利に関する国際規範の全部または一部の不遵守が、自由剥奪に恣意的な性質を与えるほど重大である場合(第3類型)
(d)亡命希望者、移民または難民が行政的または司法的な審査または救済の可能性がないまま、長期間に渡る行政拘禁を受ける場合(第4類型)
(e)自由剥奪が、出生、国籍、種族的もしくは社会的出身、言語、宗教、経済状況、政治的その他の意見、性別、性的指向、障害または他の状態に基づく差別のため、国際法の違反となり、その違反が人間の平等の無視を図る、または無視となり得る場合(第5類型)
本プロジェクトを受けて第199回通常国会参議院厚生労働委員会では、恣意的拘禁作業部会がリクエストしているカントリービジットの用意についての質疑がおこなわれた。それによると外務省は、オープンビジットなので受け入れる予定と答弁するも、準備に時間を要しているとして具体的な訪問の計画については返答をしなかった。
構成メンバー
・桐原尚之
・伊東香純
・戸田真里
・舘澤謙蔵
・高木美歩
・西田美紀