論文等
・松原洋子「『科学史研究』初期の編集・発行状況――創刊から休刊まで(1941〜1944年)」『科学史研究』第51巻、102-105頁、2012年6月
・山口翔・青木千帆子・植村要・松原洋子「電子書籍のアクセシビリティに関する出版社アンケート」『国際公共経済研究』第23号、244-255頁、2012年9月
・松原洋子「福島原発事故と生命(いのち)―研究者の倫理を考える」(第24回日本生命倫理学会年次大会報告特別講演)『日本生命倫理学会ニューズレター』第52号、1頁、2013年2月
・松原洋子・植村要「未校正書籍テキストデータの読書アクセシビリティ―大学図書館における読書障害学生支援に向けて―」『立命館人間科学研究』第26号、 99-110頁、2013年3月
・松原洋子「翻訳語としての『遺伝子』の由来」『科学史研究』第52巻、印刷中、2013年3月刊行予定
・松原洋子「妊婦の血液を用いた新しい出生前診断―ミスリードの著しいメディア報道」『あせび会だより』第197号、6−7頁、2013年3月
講演等
・松原洋子「戦後日本の医学史を斬る「母体保護」と「優生学」の狭間で」2012年4月30日、まちだ市民大学HATS公開講座、町田市生涯学習センター(招待講演)
・横山美和「女性身体の医療化のポリティクスをいかに論じるか――横山美和「女子高等教育における「月経」論争―クラークとジャコービーの栄養代謝論をめぐって」へのコメント」、2012年9月22日、生物学史研究会(日本科学史学会生物学史分科会)、東京大学駒場キャンパス
・四ノ宮成祥ほか「21世紀における生命科学研究と機微技術管理、生命倫理の新たな邂逅」、日本生命倫理学会第24回年会公募ワークショップⅡ、2013年10月26日、立命館大学(コメント)
・常世田良「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」について、R-GIRO/IRIS研究会、2012年11月19日、立命館大学(コメント)
・竹沢泰子ほか「人種神話を解体する 科学と社会の共生産」、京都大学人文科学研究所共同研究班 人種表象のグローバル日本型研究、2012年12月16日、国立京都国際会館(コメント)
・松原聡ほか「電子書籍のアクセシビリティ報告会」、電子出版制作・流通協議会、2013年1月15日、日本教育会館(指定発言)
・坂井めぐみ・利光恵子「生命科学と当事者」研究会、2013年3月17日、コンベンションルームAP品川会議室C(コメント)
プロジェクト等
・立命館グローバル・イノベーション研究機構(R-GIRO)研究プログラム「電子書籍普及に伴う読書アクセシビリティの総合的研究」代表者
・人間科学研究所研究プロジェクト「読書障害学生支援における大学図書館の課題」代表者
・立命館大学生存学研究センター2012年度若手研究者研究力強化型プロジェクト「病と社会・環境・科学技術に関する近代史研究会」代表者
・科学研究費補助金「サイボーグ医療倫理の科学技術史的基盤に関する研究」(基盤C,2010〜2012年)研究代表者
・科学研究費補助金「視覚障害当事者の共同自炊型オンライン電子図書館を実現するための条件に関する研究」(基盤A,2012〜2015年,研究代表者石川准静岡県立大学教授)研究分担者
・文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「大学を模擬社会空間とした自立支援のための持続的対人援助モデルの構築」(立命館大学人間科学研究所)情報蓄積と移行システムアーカイビングチームメンバー
・立命館大学生存学研究センター2012年度若手研究者研究力強化型プロジェクト「出生をめぐる倫理研究会」メンバー
委員等(学内)
・立命館大学人間科学研究所運営委員
・立命館大学生存学研究センター運営委員
・『立命館人間科学研究』(立命館大学人間科学研究所)編集委員
・『Core Ethics』(立命館大学大学院先端総合学術研究科発行)編集委員長
・Ars Vivendi Journal (生存学研究センター発行)編集委員
学会活動
日本科学史学会和文誌委員会委員長(2009/07-)
日本生命倫理学会企画委員(2009-)
『生物学史研究』(日本科学史学会生物学史分科会発行)編集委員(2006/12-)
日本学術会議第22期連携会員(第一部史学、2011/10-)
所属学会
日本科学史学会、日本科学史学会生物学史分科会、日本生命倫理学会、日本医療保健社会学会、科学技術社会論学会、日本医史学会


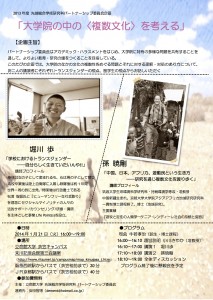 <画像クリックでPDFダウンロード>
<画像クリックでPDFダウンロード>