2019年度 博士論文/博士予備論文構想発表会
先端研では、博士予備論文(修士論文に相当)・博士論文の構想発表会を行なっています。
構想発表会は、プロジェクト型教育・学際的研究を推進する先端研ならではの、多様な関心をもつ院生・教員・研究者らが集う貴重な機会です。ぜひこの場に参加して、先端研の魅力を体感してみてください。
7月の構想発表会では、オープン交流会、コーヒーブレーク、院生・修了生の著書紹介などを行ないます。多くの関係者と交流できるチャンスですので、積極的に活用してください。
本研究科構想発表会の2つの魅力
-
コーヒーブレイク
コーヒーや冷たい飲み物をご提供します。
-
修了生・在学生の著書展示ブース。
コーヒーブレイク会場の応接室にて、先端研独自の出版助成制度で刊行されたものなど、修了生・在学生の著作の展示を行います。
2019年度 秋学期 博士論文/博士予備論文構想発表会
論題・スケジュール
開催概要
日時 2020年2月13日(木)
会場 立命館大学 衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム
2020年2月13日(木)
- 11:00~11:50 <博士>(表象)「大正・昭和におけるモダン着物デザインの葛藤」
- 12:50~13:50 <博士>(公共)「日本における胃瘻の意義および変遷に関する研究」
- 13:50~14:50 <博士>(生命)「「精神障害」を生きる当事者たちのライフストーリー就労支援の現場に着目して」
- 14:50~15:25 <予備>(公共)「外国人技能実習制度の変遷と課題」
2019年度 春学期 博士論文/博士予備論文構想発表会
論題・スケジュール
2019年7月20日(土)
- 10:00~10:35 <予備>(公共)「精神科病院における「対話」の方法―Anticipation Dialogueの日本への導入」
- 10:35~11:10 <予備>(生命)「近代日本における結核の発病予防をめぐる言説の研究―通俗医学書・雑誌を中心に―」
- 11:20~11:55 <予備>(表象)「ポール・ド・マンの「機械」と読むことの非人間性」
-昼休-
- 13:00~13:35 <予備>(公共)「Asexualityの理論構築に向けて」
- 13:35~14:10 <予備>(公共)「<沖縄的状況>で子どもを産み育てる意味―沖縄の非婚シングルマザーの生活史を中心に―」
- 14:20~14:55 <予備>(公共)「脆弱な皮膚と共にある生―表皮水疱症者の語りから―」
- 14:55~15:30 <予備>(表象)「ジル・ドゥルーズと創造―シーニュ・シミュラクル・プラトニズムの転倒―」
2019年7月21日(日)
- 10:00~10:50 <博士>(共生)「多様化するシリアスゲームと韓国社会」
- 10:50~11:40 <博士>(生命)「アイデンティティ・ポリティクスの分析から見る障害の主体―社会モデル論を手掛かりに―」
-昼休-
- 12:40~13:30 <博士>(公共)「特別支援教育における格差の存在とその要因についての研究 ―都道府県間の特別支援教育体制整備の差異に着目して―」
- 13:30~14:20 <博士>(生命)「イヴァン・イリイチにおける〈反〉近代的思想の系譜」
- 14:30-15:20 <博士>(共生)「患者の逸脱論」
- 15:20-16:10 <博士>(公共)「精神障害者のグローバルな草の根運動-連帯の中の多様性-」
2019年度先端総合学術研究科オープン交流会
講演スケジュール(予定)
- 17:30- 講師 中倉 智徳氏
(千葉商科大学人間社会学部専任講師・生命領域2010年3月修了)
「ハイパーメリトクラシーとタルドによる精神の量化について」 - 18:00- 懇親会
2019年7月22日(月)
- 10:00~10:35 <予備>(公共)「台湾における障害のある性的少数者の現在―当事者の生活史を中心に―」
- 10:35~11:25 <博士>(公共)「障害者政策の意思決定場面における当事者性の発揮に関する一考察−群馬県と前橋市の手話言語条例をめぐる議論に着目して−」
-昼休-
- 12:30~13:05 <予備>(公共)「障害のある教員の当事者団体運動の展開と対立―1990年代を中心に―」
- 13:05~13:40 <予備>(共生)「東インドネシア・スンバ島における「人-馬」関係と社会変容に関する人類学的研究」
※公聴会


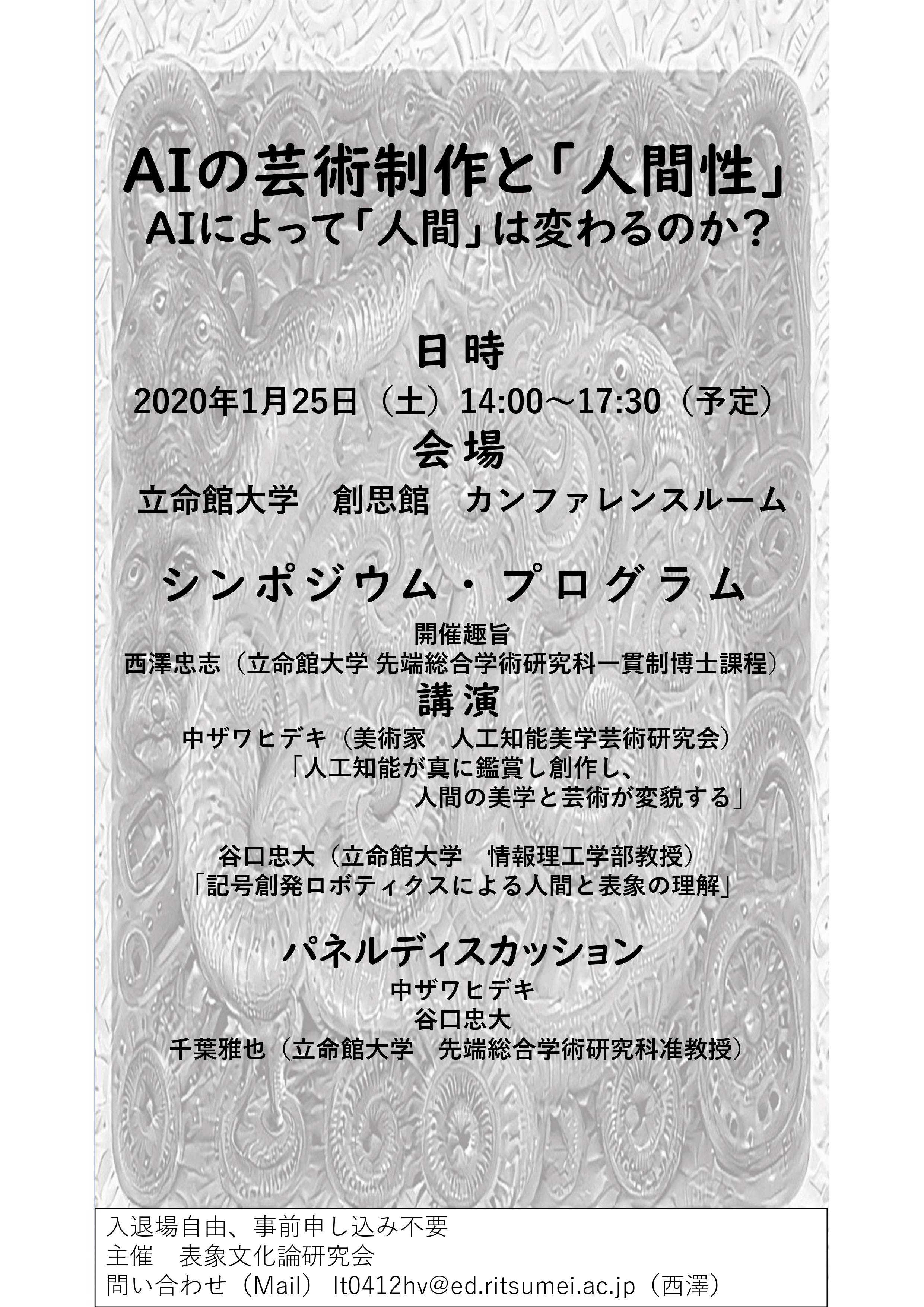
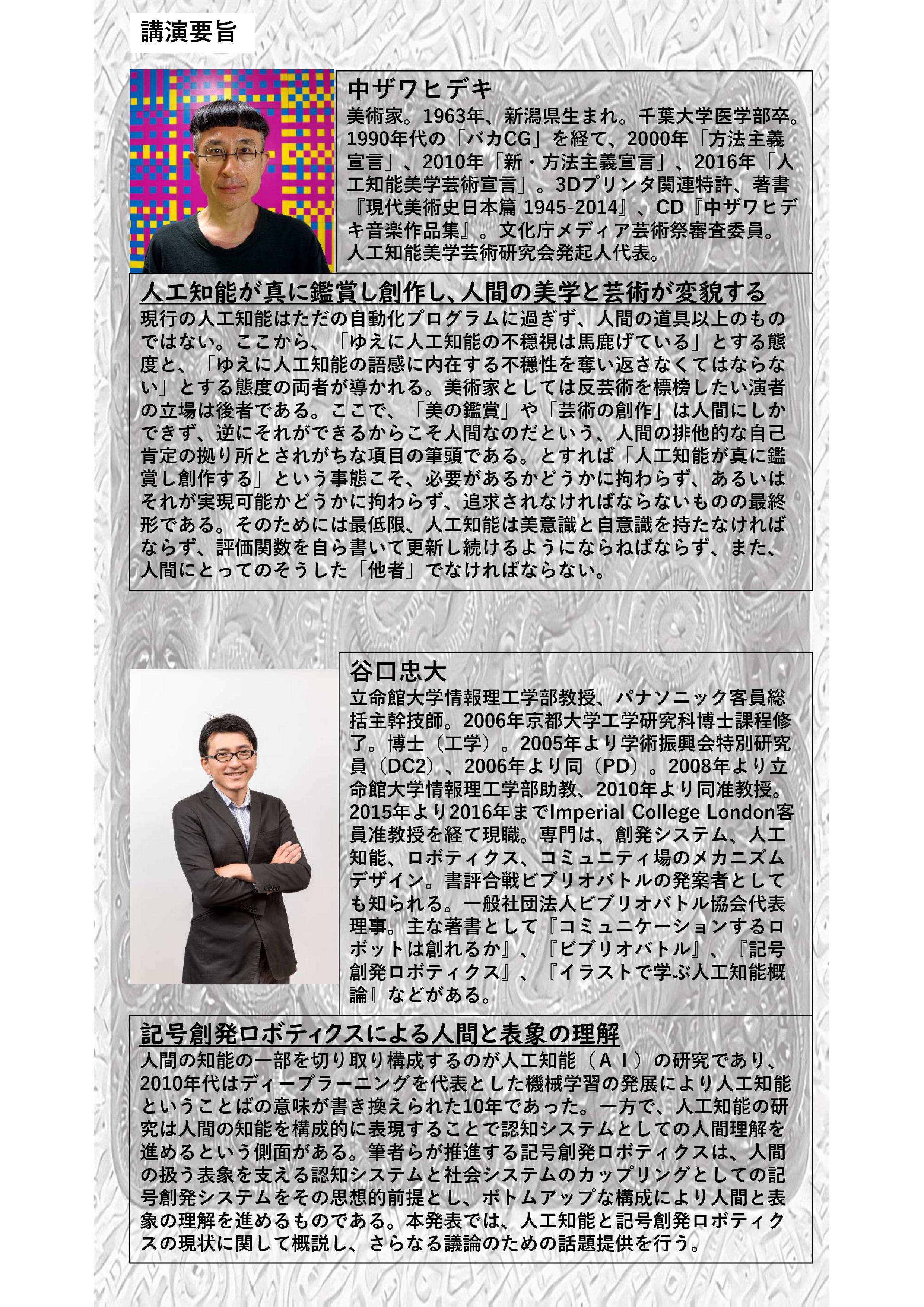
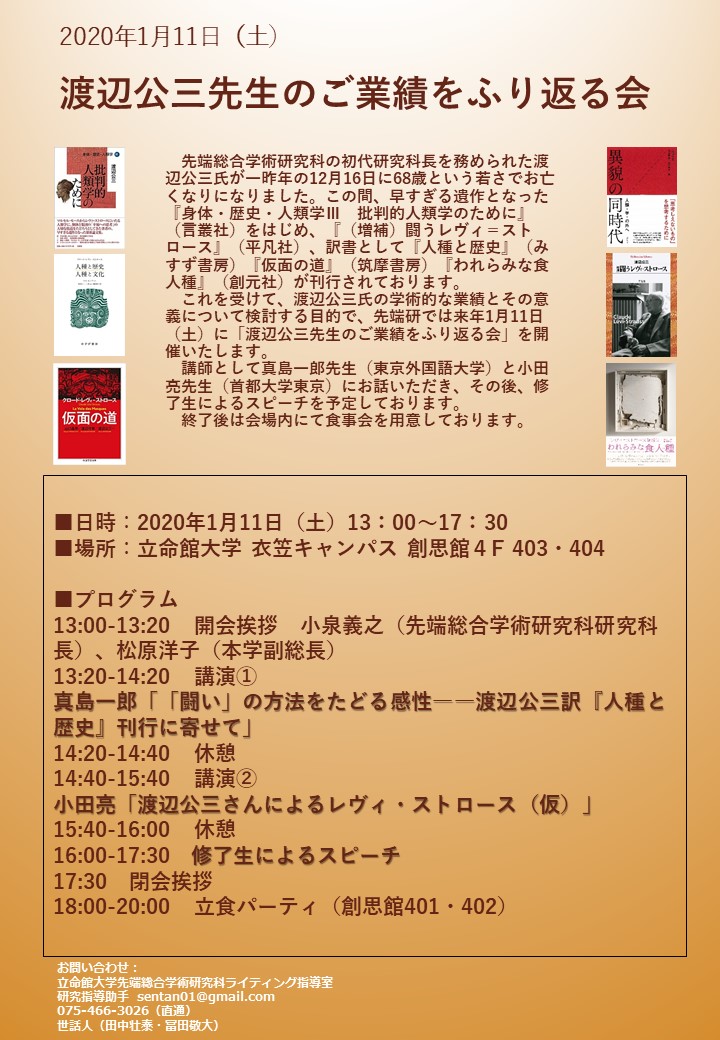
_page-0001.jpg)

