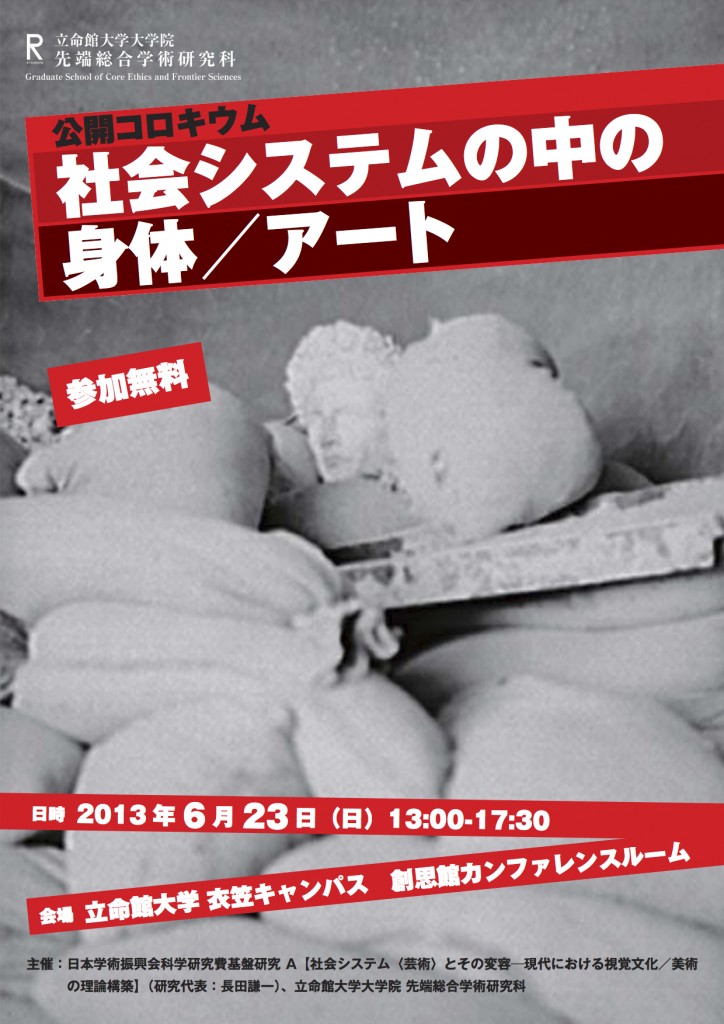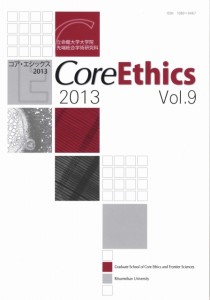国際コンファレンス
社会正義とカタストロフィ:リスク・責任・互恵性
Social Justice and Catastrophe: Risks, Responsibility and Reciprocity
カタストロフィは突然、特定の場所と時間に降りかかってくる。カタストロフィによって、社会の一部は被災するものの、それ以外は無傷のままである。正義は、その特定の被災者に対し、いかなる対応を求めるだろうか。被災者は、人道的支援や経済的な復興支援を受ける権原を超えて、いかなる権原を有するだろうか。被災者に対するわれわれの義務と被災者の権利は、どのような関係にあるだろうか。どのような支援や補償が、正義の要求するところとなるだろうか。正義の観点からは、どこまでが個人が負うべきリスクで、どこまでがわれわれが担うべき責任の範囲になるのだろうか。そしてそれらと互恵性・互酬性の理念は、どのように関係しているのだろうか。
上記テーマに関連する研究報告を、広く募集します。
開催概要
| 日時 | 2014年3月19日(水)・20日(木) |
|---|---|
| 会場 | 立命館大学 衣笠キャンパス 創思館 カンファレンスルーム |
応募要項
報告要旨(日本語の場合:800字~1,200字、英語の場合:約400 words)を電子ファイル(ワードファイルかPDF)で次のアカウントに送ってください。
justiceandcatastrophe★gmail.com(★→@)
締切日
2013年12月26日(木)厳守
(※採択の可否については、2014年1月17日までにお知らせする予定です)
報告時間
報告時間20分+討論時間5~10分
使用言語
日本語と英語(質疑応答のみ同時通訳者あり)。
(※報告原稿は日本語で用意していただいて結構です)
出版
一部の報告原稿は、『立命館言語文化研究』に掲載されます
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/lcs/kiyou.html
招待報告者
Mark Anspach (Bologna, Italy), Adam Broinowski (ANU, Australia), Paul Dumouchel (立命館大学), 後藤玲子 (一橋大学), 井上彰 (立命館大学), 中山竜一 (大阪大学), 大澤真幸, 宇佐美誠 (京都大学)
世話人
Paul Dumouchel (立命館大学大学院先端総合学術研究科・教授)
井上彰 (立命館大学大学院先端総合学術研究科・准教授)
後藤玲子 (一橋大学経済研究所・教授)